九州めぐりと寝台特急はやぶさ乗り納めツアー【3】(2008/11/22)
阿蘇カルデラの散策:
起床が遅かったこともあり車でのんびり朝食をとる時間が勿体なかったので、買ってきた団子類は走りながらパクついた。
道の駅正面の交差点の向こうに木々の生えない山がそびえたっている。往生岳というそうだ。
目の前の道を直進し、まず初めに米塚と草千里を見に行ってみることにする。
直進の道は阿蘇パノラマラインという名前が付いている。どんどん高度を上げて10分ほどで山の中腹に上がると、周囲の見晴らしがよくなった。
途中の丘に車を停めて撮影した写真。こうしてみると巨大なカルデラの様子がよく分かる。カルデラというのは噴火などによって地中にあるマグマが抜けてしまうことで、支えがなくなった地面が沈み込んでしまったものである。スペイン語で鍋という意味らしく、その名のとおり周囲を山に囲まれたなべ底のような形状をしている。
その巨大な鍋の底に阿蘇の集落が広がっている。阿蘇山が噴火したらひとたまりもない場所だが、こういう場所でもそこで生活するメリットがあるのだろう。
さらに進むと今度はいこいの村方面へ道が分岐する。その先にちょっとした駐車スペースがあったので再び車を停めてみた。
この辺は草原になっていて、写真のような柵があるとおり放牧地となっている。
奥に屏風のように立ちはだかる山は、手前が楢尾岳、奥が高岳という。
道の向こうには阿蘇駅の交差点からも見えていた往生岳の姿。だいぶ近くなってきた。

そして周囲を見回すとそこかしこに牛馬の姿が。思い思いに草を食んで日向ぼっこをしている。
黒い牛には「サ」という焼き印が押されていた。遠くからでも分かるようにしているのだろう。

ポニーみたいな馬もいた。こちらは116番らしい。背中を温めているのかな。うっとりした表情でただじっと立っていた。
さらに進んでいくと今度は米塚が見えてきた。伊豆の大室山のようなきれいな三角錐の形をした山である。牧草地として利用しているのか山には木が1本も生えていない。草で覆われた山肌はなんだか柔らかくて暖かそうな感じがする。
麓の方は牧草が刈り取られている。が、なんかまだらである。谷沿いの所を刈り残しているのは何か理由があるのだろうか。
既に冬の装いなので山肌は小麦色だが春先の新緑の季節に来ると目の覚めるような鮮やかな緑に覆われて絶景だそうだ。
米塚の方を向いてその背後、杵島岳が雄大な山容をこちらへとむけていた。太陽が真正面なのでド逆光だが、あえてそのまま撮影してみたら日本の風景っぽくない荒涼とした印象の写真が撮れた。
そしてさらに走ると今度は草千里が見えてくる。こちらも今は枯草色だが新緑の季節は見事な緑のじゅうたんになるそうだ。いつか春先の阿蘇も見てみたいものである。
ちなみにここ草千里を見学するために草千里展望台という場所が道路沿いに設けられているのだが、何故か木々の刈り払いが不十分で展望台の名に偽りありであった。上の写真は展望台から少し下った所の道端で撮影したものがこちらの道端からの方が綺麗に見晴らせた。

上の写真の下の方にも少し写っているが、土がむき出しになった所から湯気が立ち上っていた。地面の温度が高いようだ。流石火の国熊本。
この地熱のせいか分からないが、起きた時に肌寒かった気温もぐんぐんと上昇してこの辺りでは上着要らずだった。
阿蘇中岳火口へ:
さて、この道をこのまま道なりに進んでいくと阿蘇中岳の火口への道が分岐する。未だに熱を滾らせその火を噴くタイミングを虎視眈々と待ち構えているかのような大きな火口があるらしいのだが、我々はそこへは行かないつもりだった。この辺りの散策ルートの下調べをあまりしないまま来てしまっているのでそこへ行く手段が分からなかったからである。多分どこかに車を停めてひとしきり山登りをすることになるのだろうからその時間がもったいないと考えたからだ。
ところが車を進めていくと山頂展望台方面へ向かう有料道路を案内する看板があった。なに、車で登ることができるの?
気軽に立ち寄れるならせっかくだから火口も見ていくか、ということで急遽立ち寄ることにした。
有料道路の料金所で窓を開けたら、係員から心臓とか気管支が悪い方はいらっしゃいませんか?と聞かれた。硫黄ガスが多少あるので循環・呼吸器系の疾患を持っている人は入山禁止となっているらしい。
自分はごく軽度の喘息持ちなのだが、それが係員の言う悪い方に当てはまるのかが分からない。そのあたりをちょっと尋ねてみようかと思ったが、後ろに車列が続いていたので、ややこしくなるかなと思って、大丈夫ですと答えてそのまま通過した。
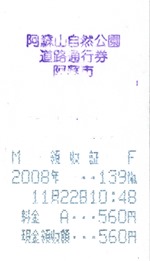
そこから数分で頂上の駐車場に到着。ここで車を降りてあとは遊歩道を散策するそうだ。辺りにはかすかに硫黄の臭いが漂っているのを感じる。やはりガチの火山地帯だけはある。
阿蘇山はバリバリの活火山で現在も時々小噴火を起している。かつてそうした小噴火の際に放出された火山弾が観光客を直撃して犠牲者が出るという痛ましい事故があったらしく、それを防ぐためのコンクリート製のシェルターが点々と設けられていた。
だが本来の阿蘇山はこれだけのカルデラを形作ってしまうほどの巨大な火山である。ここがもし破局的な大噴火をすると九州のみならず西日本が全滅するような事態にもなりかねないらしい。この程度のシェルターがそんな噴火に対応できる物だろうか・・・。今日がその日ではないことを胸の内でひそかに祈りながら散策した。
遊歩道には修学旅行で訪れていると思しき学生服姿の少年少女がいた。火口の手すりの近くで悪ふざけをしながら写真を撮っている。落ちるなよ、、、と思いながら暫くそこが空くのを待って自分も火口の縁に寄ってみた。
火口からは盛大に水蒸気を噴き上げていた。ここが阿蘇山における一番ホットな火口である阿蘇山中岳火口である。
この水蒸気の供給元は火口に溜まった池の水であるようだ。ということは池の水はぐつぐつと煮えたぎっているということだ。
一瞬湯気の隙間から水面の様子が見えた。
水の色は絵の具を溶いたかのような白っぽいエメラルドグリーンで、見ただけでダメな色だと分かる。落ちたら一瞬で命を落とすやつだ。
中岳火口の先にも遊歩道が設けられているが、そちら方面へ足を延ばす人はあまりいないようでこちらは閑散としていた。
せっかくの訪問なので自分らはそちらの方へも足を延ばしてみた。
周辺にはポコポコと火口が口を開けている。それらの火口は一番北側に位置するさっき見た中岳火口から順に南方向に第1~第7の順に番号が振られている。上の写真は第7火口と呼ばれている火口。ここは活動を休止して時間が経っているのか釜などもなく静かなものだった。
そんな感じでぐるりと一周見て回ってきた。見に来てよかった。来なかったら後でこういう場所だと知った時に相当悔しい思いをしたに違いない。ただ硫化ガスにやられたのか、車に戻った時には少しのどが痛くなっていた。
白川水源:
阿蘇山の散策を終えて阿蘇山の南麓に位置する南阿蘇村にやって来た。周辺にいくつか見所があるのでそれらを見て回りたい。
まず最初に向かったのが白川水源。阿蘇は名水の湧く里としても知られている。ここはそうした水源地のひとつだ。

白川水源はその名のとおり白川という川の水源地となっている。水源と言えば山の谷あいからチョロチョロと水が湧き出るような場所をイメージするが、ここは街中にあってこんこんと水が湧き出していた。

敷地内には水を溜める池があってそこで水が汲めるようになっていた。汲みやすいようにじょうごやひしゃくなども備えられている。
やってくる人たちはペットボトルやタンクのようなものに汲んで持ち帰っている。多くの人はタンクを持参しているようだが、入口でも販売されているので手ぶらで来ても汲んで帰ることができる。
自分らは大きなタンクに汲んで帰るほど水を必要としていない。煮炊きに使うわけでもないから消費しきれない。でも味見はしてみたい、ということでとりあえず車にあった空になったペットボトルに汲んで行くことにした。その時、はたと手が止まった。この水、非加熱で飲用して大丈夫なのだろうか。
何しろ池のすぐ脇を土足で人が歩いているのだ。靴底に付いた砂や汚れが池の中に入っているんじゃないだろうか。みんなが汲んで持ち帰っているので少なくとも煮沸してから飲めば大丈夫だと思うが、生水のまま飲んでも良いのだろうかと心配になってしまったのだ。
まぁ、ご覧のとおり水は常にさらさらと流れているので汚れても滞留することなく流れて行ってしまうだろうとは思うが、万一腹など壊したらこの後の行程が悲惨なことになる。とりあえずそのままグイっと飲む人がいれば安心できる。そういう人がいないだろうかと暫く様子を見ていたのだが、汲んで持ち帰る人ばかりでその場で飲む人がいない。やっぱり生で飲んだらダメなんじゃないか・・・。
でも入場料を払って池を眺めただけで帰るのは流石に悔しい。待ってても埒が明かなさそうなので意を決して飲んでみることにした。ら、美味かった。根拠はないがこれだけ美味いならきっと大丈夫だろうという気がしたので2人分汲んで持ち帰った。
帰宅後にネットで確認したら生水で飲用可となっていた。お腹も壊さなかったので大丈夫だ。

水源の奥にはちょっとした神社がある。白川吉見神社といい水源の水神様として祀られているそうだ。せっかくなので参拝してから次に進んだ。











