四国・山陰初日の出【14】(2009/01/03)
旧国鉄大社駅:
さて、今回の旅における山陰観光の柱のひとつである出雲大社への参拝も無事済んだので、午後はもうひとつの柱である出雲周辺の鉄道散策に繰り出すことにした。
天下に名だたる出雲大社への参拝客輸送のため、かつては国鉄大社線と一畑電鉄(現:一畑電車)大社線の2路線が出雲大社まで路線を伸ばしていた。だが国鉄大社線の方は1990年に廃止となり当時の大社駅の駅舎が保存展示されている。
大社駅跡まで出雲大社から徒歩で15分少々の距離である。徒歩15分と言ったら結構な距離だ。一方一畑電鉄はその中間地点辺りに駅を構えていて10分以内でアクセス可能である。一畑電鉄が残ったのはある意味必然とも言える。
こちらが国鉄大社線大社駅跡。1924年(大正13年)に建築された駅舎は大社線廃止まで使われていた。
入母屋形式の重厚な佇まいは出雲大社を模して造られたものだと言われており、貴重な大正建築であることが認められ2004年に国の重要文化財に指定されている。
駅舎は開放されていて内部を見学することができる。
駅舎内は広い吹き抜けの空間になっていて、現役当時は恐らくここに待合用のベンチなどが並べられていたのだろうと思う。
現役で使われていた頃の制服や道具なども展示されている。
中央にある駅務室も手の込んだデザインとなっている。特に窓口の細かな装飾は必見である。観光案内所の看板が掲げられているが現役当時からの物だろうか。現在は無人となっているので中に立ち入ることなどはできない。

そのまま駅舎を通り抜けるとホームに出ることができる。出てすぐに目に着いたのは精算所の窓口。駅務室の窓口と同様の装飾が施されていて掲げられた文字が右書きになっている。右書きの板はさほど古いものでもなさそうだったので、当時を再現するために後から付け足されたものかもしれない。
ホーム上にはD51が展示されていた。この駅には2000年の旅行の時にも一度来ているのだが、その時はまだ置かれていなかったような気がする。が、覚えていないだけかもしれない。
一畑電車の最古参電車、デハニ50形
国鉄大社駅の見学を終え道の駅に戻る。その道すがらにある一畑電車の出雲大社前駅にも立ち寄ってみた。

上述のとおり一畑電車の方は現在も営業を続けている。駅は1930年(昭和5年)に建築され、国鉄の大社駅に対抗してステンドグラスが嵌められた教会風の様式でまとめられている。こちらも駅舎が国の登録有形文化財に登録されており、国鉄大社駅と並び貴重なものとなっている。
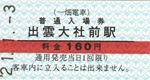
こちらの駅に立ち寄ったのは入場券を買いたかったからというのもあるが、一畑電車に唯一残る旧型車であるデハニ50形の情報を仕入れるためである。まだ引退はしていないことをネットで確認しているが、普段どこに停められているのかや運行している場合の運転時間などが分からなかったので駅で聞いてみようと思ったのだ。
駅の係員に声をかけて質問してみると車両は雲州平田駅に隣接する車庫に留置されている、という情報を得ることができた。そう分かれば善は急げ。お礼を言って雲州平田駅へ向かった。
道の駅の駐車場に戻ったら車があふれていた。停められそうなところには路肩や通路を問わずみっちり車が停められている。それでも入りきれない車が道路に列をなしている。昨晩頑張ってここまで運転しきった自分を褒めてやりたい。
で、車を出庫させ温州平田駅へと向かう。宍道湖畔に位置する雲州平田駅まで20分ほどの道のり。

ということでやって来た。
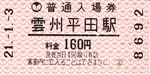
入場券を入手したのち駅の係員に声をかけて車庫見学の可否について訪ねた所、車庫の詰所の方で聞いて欲しいとのこと。言われるがまま車庫の詰所に向かって、そこにいた係員に再び見学の申し入れをしたらすぐに承諾が得られた。
係員がアテンドしてくれるというので、しばし待って準備ができたところで車庫へ移動。
こちらがデハニ50形である。かつては同形態の車両が多数配置されていたが、南海21000系や京王5000系の入線により徐々に引退し、現在ではこの1編成のみとなってしまった。
自分が鉄道ファンの世界に足を踏み入れた当時はまだこの形の車両が幅を利かせていて、昭和レトロな車両は一度見てみたいと思っていたのだが、流石に出雲は遠すぎて訪ねる機運すら盛り上がらなかった。
かつて釣りバカ日誌の映画の1シーンでこの車両が写っているのを見た記憶がある。扉を半開きにしたまま走り去る列車に乗り遅れたハマちゃんが慌ててホームを追いかける、みたいなシーンだったと思う。そう、扉が半開きだったのだ。この車両は昭和3年に製造されていて製造当初から扉が手動式になっている。その後も自動化されることはなく、現在に至るまで手動扉のままとなっていて日本で最後の手動扉の電車であったそうだ。
前回、2000年の訪問時もこの車両を求めてこの地まで訪れたのだが、その時は遭遇できずじまいだった。車齢80年を迎える古老であり、もはやいつ引退の声が聞こえてきてもおかしくない状態だったので今回どうにかお目にかかりたいと思っていたのだった。そしてその読みどおり、訪問から2カ月ほどたった3月をもって引退となってしまった。本当にギリギリでの訪問だった。
というわけでちょっと堪能したいので、しばしお付き合いのほど。

ご覧のとおり扉は手動扉である。わざわざ窓にそう書いてあるのは自動扉と間違えないようにだと思う。地方では扉が半自動で駅に到着した時にボタンを押さないと開かなかったりする。都会にいると扉は勝手に開くものなのでうっかり扉の前で立ち尽くしてしまい、地元の人が呆れ交じりの表情でボタンを押したりする姿を何度も目撃している。手動で開けなければならないのであればなおさらであろう。

車両はカギがかけられていて車内の見学は叶わなかったので窓越しに車内を覗いてみた。運転席は武骨で質実剛健な作りである。内装は木が使われていてぬくもりを感じる設えである。と言っても当時はそれが普通だったのだが。
デハニ52形の反対に連結されている車両がデハニ53である。同じ形式に属する車両だが、こちらは窓枠がアルミサッシに更新されている。
写真のように車両には扉が3つ付いている。最前部の扉とその直後の扉の間に荷物室が設けられているため、デハ”ニ”を名乗る。
国鉄(=JR)や一部の私鉄ではモハ・クハと言った分類名が採用されているが、私鉄で多いのがこのデハという分類名である。デハの”デ”はもっぱら「電車」や「電動車」の頭文字である。こういうのを統一しないので分類好きな鉄道ファンがはびこることになるw

ドアの取っ手は真鍮製と思われ年季が入っている。カーキ色のような鈍い色合いに過ごした年月の長さを感じる。

そして、車体はリベット打ちされていてこれもまた古い車両であることを静かに主張している。
当時の電車には乗務員扉が備えられていないものが多い。客用扉から一旦客室に入ってそこから運転台へと移動する形式だが、混雑中に運転台からの出入りがしずらくなる懸念があり近年の鉄道車両は乗務員用の扉が別に付けられている。この電車も乗務員扉のない車両である。
そして最後に1枚。無事に撮影ができてよかった。

お礼を伝えて車庫を後にしたら、雲州平田駅に丁度列車が到着するところだったので少し待ってみたら、元南海21000系の3000系だった。この車両も相当な老兵であるがデハニ50形から比べたらまだ若造である。







