岡山出張【10】(2023/09/17)
園内散策 - 西側エリア:
その放送を聞きながら残りの坂道を登り切って丘の上に出た。この先にも住居棟がある。こちらはこれまで見てきたものより前に建てられたものらしく見た目が少々くたびれている。
建物の後ろ側に増築した形跡がある。増築された箇所に給湯機があるのでこのエリアの建物はお風呂が後から増設されたのだろう。
そして通りに沿って配管が延々と連なっている。
で、この辺にあったスピーカーから再びラジオ放送が聞こえてきたのだが、坂道で聞いたラジオのDJがさっきと同じクイズを出していた。あれ、放送がずれている。園内のスピーカーから流れている放送はリアルタイムじゃないのか。
ということはどこかでラジオ番組を再配信しているのだろうか。それにしても時差があるのが解せない。何らかの意図(例えば最初のスピーカーからこのスピーカーまでの間の距離感を図るため、とか?)があって放送の時間を意図的にずらしているのだろうか。なんか非日常のような街をずっと見て回っているせいか脳みそがひとつひとつを疑ってかかっているような感じがした。
それはさておき、愛生園の敷地を巡っていてなんか妙な既視感があるなと思っていた。既視感というか雰囲気といった方が正しいか。
現地ではそれがなんだか分からなかったが、帰宅後に写真を見ていてピンときた。軍艦島だ。もちろん愛生園と軍艦島では見た目に何ら共通項はない。私企業と国営という違いもある。たが在来の島民がおらず古くから地場で暮らす人の営みが全く見えないところや、自然豊かな場所に唐突に極めて人工的な街ができあがっている違和感、URや自治体が運営している団地となんとなく違いを感じる作りの差、そこはかとない窮屈さ、といったあたりがなんだか軍艦島を見に行った時に感じたものとダブったのだった。

更に進んでいくと電話ボックスがあった、が、中の電話は家庭用の電話機に置き換えられていた。ほこりをかぶっているので長らく使われていなさそうだが無料で通話できるのだろうか。
なんか、いのちの電話っぽくてちょっとドキッとした。

その少し先にあるのが愛誠訪問宿泊所。その名のとおり面会に来た家族などが宿泊する為の施設である。

そしてその先に有るのがむつみ交流館という建物。こちらも宿泊施設が設置されている。この施設は入所者に縁のない単なる見学者であっても、事前に申し込みをすることで無料で宿泊できるそうだ。
その脇の道をまっすぐ登っていくと、また例の案内看板が見えた。十坪住宅の横に(徳島路太利)と書かれている。とっくり?
カッコ書きのフリガナを見るとこれで「とくしまろーたりー」と読むらしい。 あまり見たことのない単語だが、どういった謂れの物だろうか。
登り始めてすぐ、ひとつ上の写真にも写っているが、小ぢんまりとした住宅が見えた。これが園に残る十坪住宅のひとつ母の家だ。
10坪だから畳20枚分ほどの大きさである。6畳と4畳半に水回りで大体16畳前後になるのでそれよりは広い。街中の狭小アパートに比べたら広々しているというくらいの大きさだったようだ。
よく見ると基礎らしきものがほとんど見えない。恐らくベタ基礎の上に直接建物が建てられているようだ。その点では快適性に多少の難があったかもしれない。
更に登って坂道のてっぺん付近にもう一軒、敷地の奥に小ぢんまりと佇む平屋が見えた。こちらが徳島路太利らしい。
ひと気はなく扉も閉まっていたので窓越しに中を覗いてみたら、この住宅に関するパネルが展示されていた。ああ、間近で見てみたいなぁ・・・。
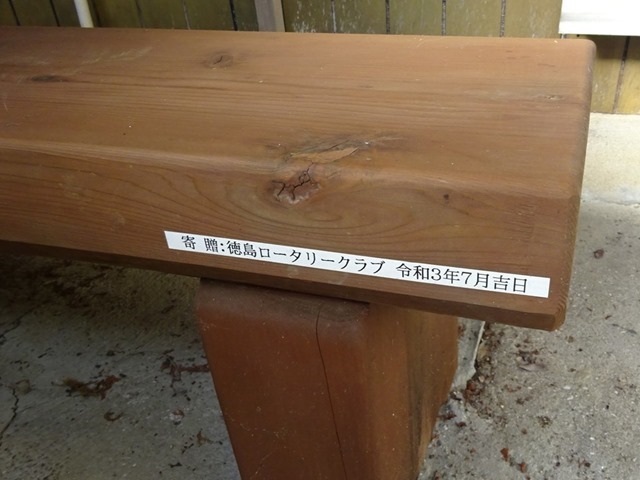
軒先に置かれたベンチに「寄贈:徳島ロータリークラブ」とシールが貼られていた。路太利とはロータリークラブのことだったか。いやそこはカタカナ表記でよくない?
なんかひざの力が抜けた。
峠の向こう側にも住居棟が建ち並んでいる。だがこのエリアから島のセンター地区へ行くためには山を登り降りしなければならない。入所者の平均年齢が80歳を超えるというのだから、こんなバリアフルな場所はあまり人気がなさそうだ。住居の割り当ての際に希望を聞いてもらえるのかは知らないけど。
園内散策 - 北~北西エリア:

そこから北西側に飛び出た小山の方へと進んで、もう一頻り遊歩道を登ると納骨堂がある。
かつてこの島に収容されるということは一生島の外に出られないことを意味していた。不幸にしてここで生涯を終えたとしても引き取る親族がいない人も多くそうした無縁仏を供養するために建てられたものだそうだ。
この中には3000柱からの遺骨が眠っている。歴史館の中には「考えてほしい。なぜ療養所に納骨堂が必要なのかを。」とだけ書かれた印象的なパネルがあった。
近年では偏見や差別が薄まってきたせいか遺族が名乗り出て引き取っていくこともあるそうだ。
納骨堂から降りて来ると変則的な五差路になっている。これから行こうと思っているのは左の赤い舗装の道である。
この急坂を降りていくと目白寮跡と解説板が出ている広場があった。
ここには元入所者の詩人明石海人という人が暮らしていたそうだ。
更に降りていくと広場に出る。その左側の片隅にコンクリート製の貯水槽のようなものが見える。これは監房と呼ばれる施設の跡である。
施設に収容された者の中には荒くれ者や逃走を企てる者がいたりする。そうした者が施設の職員によって捕らえられるとここに入れられたという。
ちなみに、仮に脱走を企てても目の前に横たわる僅か数十mの瀬戸は流れが速く溺れる者が多数いたという。また万一泳ぎ切って対岸に上陸したところで園内着を着ているうえに所持金もないので、どこへも行けないまま見つけ出されてここに連れ戻されることがほとんどだったという。
この施設は一種の治外法権になっており、所長に懲戒検束権が与えられていたことから入所者を逮捕監禁することができた。逆に言えば入所者には公民としての権利が与えられていなかったということでもある。

この監房は窓のひとつもない。真っ暗なところに閉じ込められ、食事の回数を減らされ治療も行われなかったため、収監された後にここで死亡するものも多くいたそうだ。
現在は埋め立てられたため山の斜面の一部のようになっているが、元々は独立した建物があったそうだ。
そしてさらに進んでいくと古めかしい建物が見えてくる。ここは収容所だった建物で回春寮と呼ばれていた。
回春といえば、衰えた男性がその機能を回復するこを指す言葉のイメージがあるが、いくら何でもこの施設の名前にはそぐわない。そこで辞書を引いてみたら、
1.春が再びめぐってくること。新年になること。2.若返ること。3.病気が治ること。快復。
という意味を持つ言葉であるそうだ。恐らくここでは3.の意味で使っているのだと思うが、そう考えると何とも白々しい名前である。
連れて来られた入所者は、まずここで所持品をチェックされ持ち込み禁止品は接収された。また現金は上述の園内通用票と交換され、入所者自身および所持品は全て消毒させられた。

この建物も入口の扉は閉ざされていて中にひと気はなかったが、物は試し引き戸を引いたら施錠されていなかった。中を見学させてもらおうかと思ったが誰かに咎められることを危惧して入口から覗くだけにしておいた。
だが驚くべきことに、この建物内はグーグルのストリートビューで見ることができる。興味がある方はぜひ。というか、ストビューの記録があるということは内部見学可能だったのかもしれない。更にいうと先ほどの徳島路太利も同様だったのだろうか。扉が開くかチェックすれば良かった・・・。

目の前の駐車場の一角に崩れ落ちた桟橋が見えた。この桟橋は収容桟橋と呼ばれるもので入所者がまず上陸するのがこの場所だったそうだ。
ここからもう少し歩くと歴史館の所に戻って来る。時間的にタイムアップであったのと暑さでバテてしまったのとで、見学はこれにて終了とした。
正直な所、この島を訪れるまでは単に島の上陸記録を伸ばすことをメインに、可能ならちょっと歴史館も覗いてみるか位の軽い気持ちでいた。だが前述したとおり、下調べをしているうちにこの島へ訪問することは予想外に重たいテーマであることを知った。流石にエントリにも受け売りの情報だけを書くわけにはいかないなと思い、現地のみならず帰宅後も含めてがっつりと勉強する羽目になった。そりゃもう軽い気持ちで訪問しようとしたことを後悔するほどに。
この感染症について調べるのは正直言ってだいぶくたびれた。がその一方でもう少し知ってみたいという思いもわき上がってきた。そうした矢先、カミさんから樹木希林さんが演じる「あん」という映画の上映会の話が舞い込んだ。この映画はまさしくハンセン病元患者の今が描かれている作品だった。施設の外へ出ることに何の制限もなくなって自由の身となったのに、社会復帰をしようとした矢先に未だに払拭できずにいる偏見や差別に直面するというストーリーだった。自分にとってタイムリーな話題をテーマにしたその映画を、近年まれに見る没入感でもって鑑賞した。
で、映画内で東京は東村山にある多磨全生園という施設でのシーンがあったのだが、それを見てその施設の存在を思い出した。かつて都内に暮らしていた頃、埼玉の坂戸にある実家へ一般道経由で帰る時に全生園の前を幾度となく通り過ぎていたのだ。だが当時はこの施設がハンセン病療養者が入所する施設であることは知らず、やがて坂戸へ帰ることもなくなってしまい、記憶から消えてしまったのだ。
この施設にも資料館があるそうなので、機会があればそちらの方も見学しに行ってみようと思う。そして長島の施設も光明園を含めあちこち見逃してしまった所があるので、こちらもまたいずれ再訪してみたい。











